11月のごみ拾い
こんにちは!
今回は11月のごみ拾いの様子をお伝えします📸
本日はたくさんの保護者の方にお声がけいただきありがとうございます🙇
わざわざ車を止めてお声がけいただいたり、ご自宅に入られる前に声をかけていただいたりと大変恐縮です
引き続き継続していければと思いますので、どうぞよろしくお願いします!

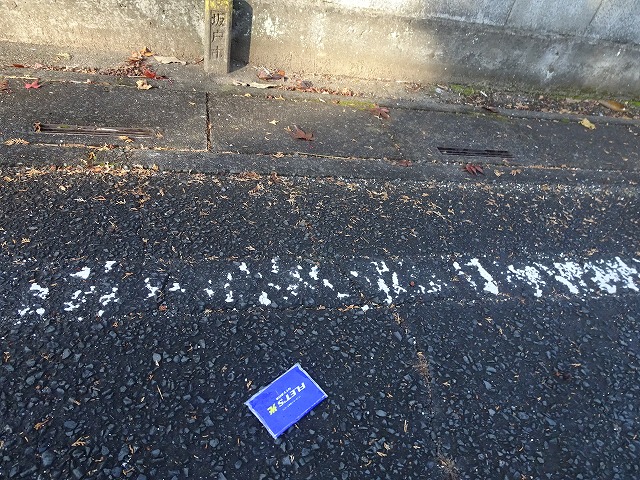



2回目の遭遇



なぜ湿布のフィルムが外に…笑

最近地区のごみ拾いがありましたので、今月は少なめでした✨
ごみ捨てはバスの先生にお願いしちゃいます🙇<オネガイシマス‼

「ファーストペンギン」の話🐧
先日、園外保育で動物園に出かけました。
子どもたちに人気だった動物のひとつが、ペンギンです。
水辺のそばをちょこちょこ歩いたり、勢いよく水の中に飛び込んだりする姿に、子どもたちだけでなく大人もつい見入ってしまいますね。
プールのふちで、ペンギンたちがじっと様子をうかがっている時間があります。
「飛び込みたいけど、どうしようかな」というように、何羽かが行ったり来たりしている中で、思いきって一羽が水に飛び込む。
すると、そのあとを追うように、次々とペンギンたちがドボン、ドボンと続いていきます。
こうして一番最初に飛び込むペンギンのことを、「ファーストペンギン」と呼ぶことがあります。
■ファーストペンギンって、どんな意味?
もともとは、氷の上から海に飛び込んでエサをとりに行く野生のペンギンの様子がイメージのもとになっています。
海の中には、魚もいるけれど、天敵もいるかもしれません。
それでも、誰かが最初に飛び込まないと、みんな何も始められない。
そんな時に、一羽目として勇気を出して飛び込むペンギンが「ファーストペンギン」です。
今ではビジネスや教育の世界でも、「新しいことに最初にチャレンジする人」「誰もやっていないことを始める人」という意味で、よく使われるようになりました。
最初の一歩を踏み出すのは、正直なところちょっと損な役回りにも見えます。
失敗したら目立ってしまうし、「うまくいく保証」はどこにもありません。
それでも、「誰かがやらなければ、何も変わらないよね」と思って動き出す人のことを、「ファーストペンギン」と呼んで、そして尊敬の目で見たいなと思います。
■子どもの毎日は、ファーストペンギンの連続
この「ファーストペンギン」の話は、大人の社会だけでなく、子どもたちの世界にもぴったり重なります。
・初めての遊具に、一番に登ってみる子
・いつも遊んでいない友だちに「いっしょに遊ぼう」と声をかけに行く子
・発表のとき、「最初にやる人?」と聞かれて、そっと手を挙げる子
・転んで泣いている友だちに、誰よりも早くハンカチを持って駆け寄る子
こうした一つ一つの行動は、子どもたちにとっての「海への飛び込み」です。
うまくいくかどうか分からないし、ときには恥ずかしい思いをすることもあります。
それでも、「やってみたい」「言ってみたい」と思う気持ちに背中を押されて、子どもたちは毎日の中で何度も何度も小さなファーストペンギンを経験しています。
■大人ができることは、「最初の一歩」が損にならない空気をつくること
新しいことや少し変わったことをしていると、それがどれだけ人のためであったり、正しいこと、社会のためになる行いであっても、すぐに足を引っ張ったり、「どうせやっても無駄だよ」と冷笑する人がいるものです。
また、「ほかの人はそんなことやっていない」と、多数派に飲み込まれるような意見をまるで正しさの基準のように振りかざす人もいます。
そういう空気の中では「最初の一歩」を踏み出した人ほど傷つきやすく、次に続こうとする人も育ちにくくなってしまいます。
本当は、ファーストペンギンのあとに続く二羽目、三羽目を増やしていきたいのに、
「目立つのは嫌だから」「変わっていると思われたくないから」と、心のどこかでブレーキがかかってしまう。
大人の世界でも、子どもの世界でも、そういう場面は少なくないのではないかと思います。
だからこそ、ファーストペンギンが育つかどうかは、「最初に動いた人が損をしない環境かどうか」に、すごく左右されるのだと思っています。
子どもたちの環境に置き換えれば、
・真っ先に手を挙げた子を、笑わずに、きちんと聞いてあげること
・うまくいかなかったチャレンジにも、「やってみたこと」そのものを認めてあげること
・「どうせ無理だよ」と水をかけるのではなく、「やってみたら、どうなるかな」と一緒に考えてあげること
大事なのはこうしたまなざしを、大人側が持てるかどうかです。
■大人だって一歩踏み出したい
僕がごみ拾いをしていても、きっと疎ましかったり、行動自体を冷ややかな目で見ている人や
「なんでそんなこと」「目立ちたいだけだろう」と言う人もいるでしょう。
それはそれでいいのです。わざわざ否定もしない。
でも、今朝のようにわざわざお声がけをしてくださる保護者の方々や先生、少しでも共感してくれる人や今後、「せめて路上にごみを落とさないようにしよう」そう思ってくださる方々。
そのようなみなさんはもう1羽目のペンギンだと思うのです。
一つ一つの行動はもしかしたら小さいものかもしれなくても、ゆくゆくそれを見た幼稚園の子どもたちが2羽目、3羽目と続いていけるきっかけとなればと強く思っています。
そしてごみ拾いに限らず、大人だって
・誰も拾っていないゴミを、黙って拾ってみる
・誰も声をかけていない人に、先にあいさつしてみる
・会議や話し合いで、最初に「私はこう思います」と言ってみる
・大勢の声に押しつぶされそうな「正しさ」に、そっと寄り添ってみる
こんなことを少しずつ積み重ねていければなと。
子どもたちは、大人の背中をよく見ています。
大人が「最初の一歩」を当たり前に踏み出している姿を見ていれば、「自分もやってみようかな」と思える回数は、きっと増えていきます。
誰が一番最初に海に飛び込むのか。
そして、その姿を見た子どもたちが、いつかそれぞれの場面で「自分なりの海」に飛び込んでいけるように、そっと背中を押していける社会になっていけばと思います。
 本日の様子
色付けのようす🖌
本日の様子
色付けのようす🖌 


