外遊び!
こんにちは!
今回はお外遊びの様子をお伝えします📸
さて、今朝は久々に外気温も落ち着き
みんなで外遊びを楽しみました☺
外で思い切り体を動かすととても楽しいですね!














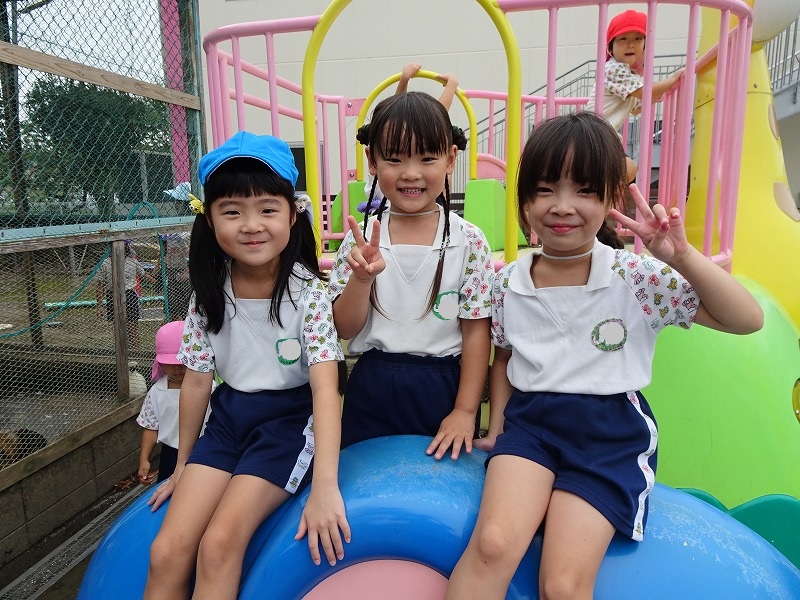




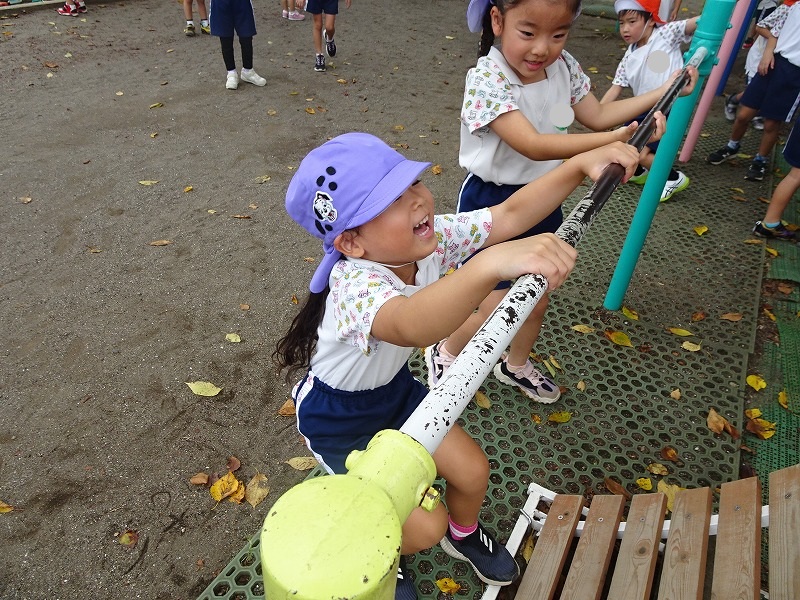



















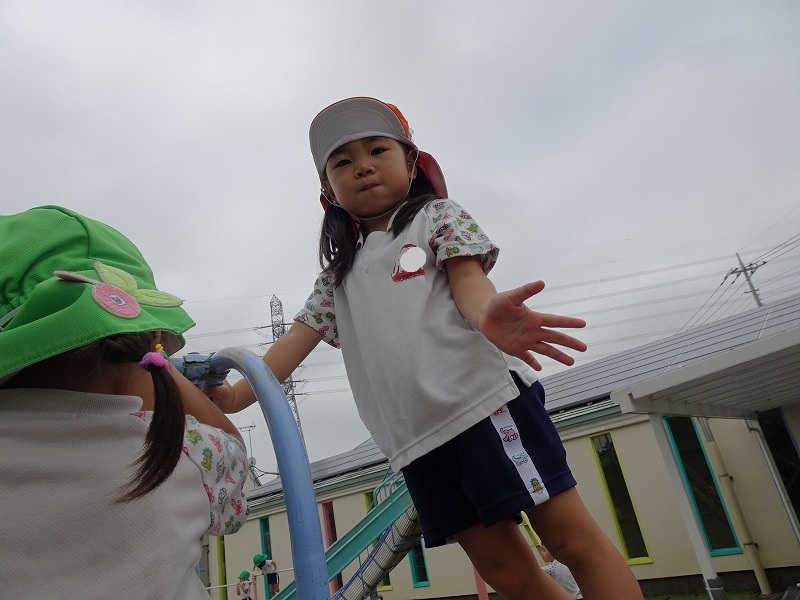


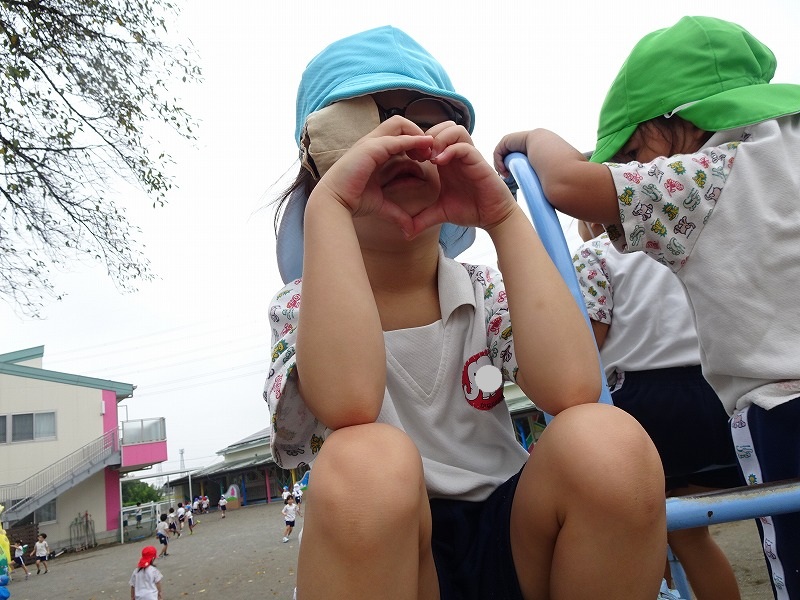
魔法の言葉「先生に言うから!」
「先生に言うから!」
園でよく耳にするこのひと言は、子どもにとって“万能な呪文”のように響きます。
この業界ではなかなかタブーな領域の話ですが、あえてこの魔法の言葉について考察してみましょう。
ケンカの最中でも、遊びの順番でも、ルールが曖昧になったときでも、すっと取り出される切り札。
とはいえ、この言葉は脅しでも甘えでもありません。
発達のプロセスの中でとても自然な“助けを呼ぶ”サインであり、社会のルールを確かめたい気持ちの表れです。
ここでは年齢発達に沿って、この魔法の正体と大人の上手な付き合い方をまとめます。
●「先生に言うから!」の正体
この言葉には主に以下のような役割があると考えられます
・境界線の確認:
自分の領域(おもちゃ・居場所・気持ち)を守りたい。
けれど幼児期は言葉や交渉がまだ未熟です。
そこで第三者=先生という“ルールの象徴”を呼ぶという行為に至ります。
・安心の呼び出し:
不公平・不安・怖さを感じたときのSOS。
一人で抱えず「頼っていい」という健康的なヘルプシーキングですね。
・ルールの内面化の途上:
外にある先生の基準を借りて、内なるルール感を育てていく途中段階。
●発達段階別の「先生に言うから!」
・年少(3〜4歳):
「守ってほしい」の合図
この時期はことばの爆発期です。
思いは強いけど、交渉語彙はまだ少なめです。
善悪は“感じ”で捉える段階。
よくある場面:「私の!」「やめて!」が通らず、最終手段で「先生に言うから!」。
→「呼んでくれてありがとう。“いや”って言ってみよう。言えなかったら一緒に言おう。」(意志の伝え方の提案)
・年中(4〜5歳):
「公平」を求めるレーダーが芽生えます。
背景:順番・交代・ルールの概念が育つ時期です。
「ずるい」を敏感にキャッチします。
よくある場面:
ルールが曖昧な遊びで揉めると「先生に言うから!」が早出しされる。
→「先生に言うのはいいね。その前に“あと3回で交代ね”って言ってみよう。砂時計も使おう。」(対応の提案)
・年長(5〜6歳):
「理由+交渉」で“内なる先生”を育てる
相手の気持ちの想像や因果を言葉にできるように。
自制の練習期です。
自分の主張は言えるが、詰まると「先生に言うから!」で勝敗を委ねがちです。
「困ったね。“理由+提案”で伝えたらどう?近くで見守っているね。」(解決方法の提案)
●使いすぎのサインと見分け方
以下のような場合は”魔法の言葉”に頼りすぎていると考えられる場面です。
適切に向き合っていきたいですね。
・“脅し”としての乱用:
相手を黙らせる目的で多用。
Iメッセージ(私は〜してほしい)へ言い換え練習。
・“チクり”と“報告”の混同:
安全・暴力・身体危険などは即報告が正解。
嫌だった/もめた、はまず自己表現と交渉を試す。
・“勝ち負け”の道具化:
先生の権威を勝敗のハンコにし始めたら、合意形成の体験を意図的に増やす。
子どもを見ていると苦笑いすることもありますが、実は頼るスキルは健全です。
多くの大人もつい、外部の権威を借りて物事を動かそうとします。
違いはそこに対話と提案があるかどうか。
大人の私たちが“理由+提案+合意”で進める背中を見せることが、子どもにとって最高の教えになることかと思います。
● 魔法の言葉は“内側”に
「先生に言うから」は、幼児期において困ったときの“保険証”です。
ただ、この保険だけで生き延びると、大人になって『もういい!』で会話を強制終了したり、不機嫌で通行止めを作ったりしがちです。
権威カード、沈黙カード、機嫌カード…形は違えど、どれも“自分の言葉で合意を作る”練習が不足したサインです。
園では“自分の声→提案→助けを呼ぶ”を練習にして、将来の“機嫌まかせ”の合意形成を予防します。
「先生に言うから!」は、未熟さの印ではなく、社会のルールに手を伸ばす前向きな発達段階です。
外側の先生を呼ぶところから始まり、やがて心の中の先生が育っていきます。
自分の声→交渉→助けを呼ぶの順路を一緒に練習できれば、魔法は“脅し”ではなく対話の道具に変わっていきます。
私たち大人も、つい外の権威に頼りたくなる瞬間に気づいたら、まず自分の言葉で提案から。
子どもたちは、その背中をよく見ています。
 ひよこちゃんのようす🐤
うんどうかいのおゆうぎ
ひよこちゃんのようす🐤
うんどうかいのおゆうぎ 


